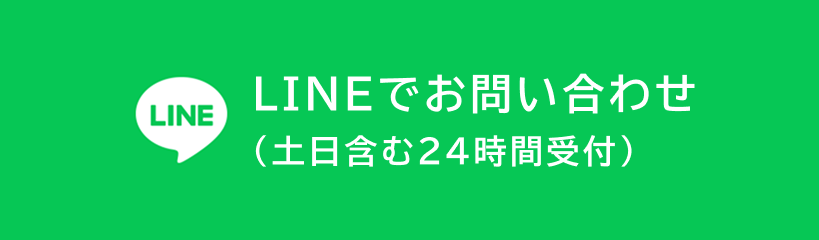社宅家賃の算定のやり方研修
発行: 2025.09.18
/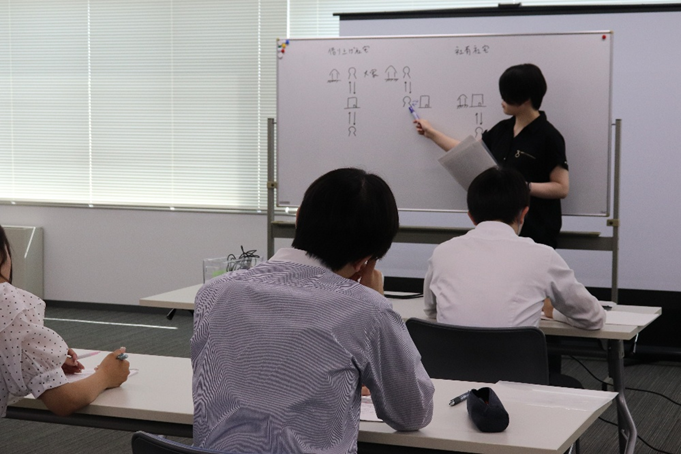
<研修の目標・目的>
・社宅の概念を理解する。
・社有社宅と借り上げ社宅の違いについて理解する。
・社宅の金額の算定方法を理解する。
・社宅の会計処理について理解する。
・社宅の税務上の取り扱いについて理解する。
<研修の内容>
今回の研修では、社宅のメリットや留意点について学びました。社宅の取り扱いについては、以前給与計算の研修を受けた際にも理解に戸惑う人が多かった点であるため、社宅の概要・種類や会計処理、税務上の取り扱いなどを時間をかけて幅広い観点から説明をしていただきました。
借り上げ社宅は住宅手当と比べ税金や社会保険料を抑えることができ、また、社宅家賃が損金として計上できることから法人税の節税にもなるというメリットがあります。しかし、賃貸借契約を締結する際に法人名義で契約を締結する必要があることや、自己負担額を徴収する必要があるという点に気をつける必要があります。
また、社宅の自己負担額を算定する際には、土地や建物の面積や、固定資産税の課税標準額を考慮して計算する必要があります。
固定資産税の課税標準額は3年に1度改定されるため、定期的に見直し、再評価をする必要があります。
<感想>
今回の研修を通じて、社宅制度の有用性について理解を深めることが出来ました。
役員や従業員に社宅を貸し付けた場合、役員・従業員は少ない自己負担額で家に住むことができ、会社としては役員・従業員の自己負担分を除いた金額を損金として処理することが出来ます。社宅は貸す方、借りる方の両者にメリットがある制度なのだなと感じました。
その一方で、会計上・税務上は非常に複雑で処理が難しい制度だなとも感じました。
社宅家賃のうち自己負担分として徴収した金額は、消費税非課税として処理しなければならないという点、社宅家賃の自己負担額を算定する際には複雑な計算が必要になるという点に今後は留意していきたいと考えております。